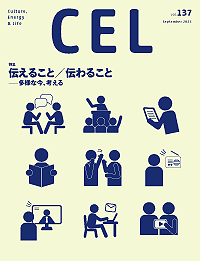河瀬 隆
2005年09月30日作成年月日 |
執筆者名 |
研究領域 |
カテゴリー |
媒体(Vol.) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2005年09月30日 |
河瀬 隆 |
住まい・生活 |
その他 |
情報誌CEL (Vol.74) |
ページ内にあります文章は抜粋版です。
全文をご覧いただくにはPDFをダウンロードしてください。
「納棺夫」という言葉に初めて接したのは、『納棺夫日記』(一九九三年 桂書房刊/一九九六年 文春文庫増補改訂版)という本だった。著者の青木新門氏は、もともと詩人であり小説家でもあった。若き日、作家の吉村昭氏に見出され、氏が編集委員を務める文芸投稿誌「文学者」にも作品が発表されている。青木氏は「納棺夫」という仕事を通じ、何ものも侵すことのできぬ静謐さを漂わせた「死者」を見つめることをとおして、深い眼差しから「生」の根源的意味を問いかけてくる。
「納棺」の仕事に就いた経緯を、青木氏は同書の中でこんなふうに記している。
――当時、青木氏は何をやってもうまくいかない。自ら始めたパブ喫茶も放漫な経営により倒産させてしまい、わが子のドライミルクも買えない困窮の中、偶然目に留まった新聞の求人欄を頼りに葬儀社に就職する。そして程なく、自然の成り行きのように納棺の仕事をするようになる。しかし富山の狭い田舎町のこと、そのことを伝え聞いた分家筋の叔父が突然訪ねて来て、その仕事を辞めるよう迫るが、青木氏の心は逆に意地になっていく。ある時、ある家の人に「納棺夫」と言われたことから、やや自虐的に自らもそう呼ぶようになる。
そんなある日、青木氏が呼ばれて行った家は、何とかつての恋人の実家。横浜に嫁いだはずの彼女は来ていないかもしれないと思い、意を決して入っていく。幸い当人の姿は見えない。ほっとして湯灌を始める。そのうち、いつもの緊張感で額から汗が落ちそうになる。それを白衣の袖で拭こうとしたとき、「いつの間に傍に座っていたのか、額を拭いてくれる女がいた。澄んだ大きな目一杯に涙を溜めた彼女であった」。退去する自分に、両手をついて丁寧に礼を言う彼女の弟らしい喪主。その後ろに立ったままの彼女。青木氏には、涙を溜めた彼女の目が「何かをいっぱい語りかけているよう」に思えてならない。それは「軽蔑や哀れみや同情など微塵もない」何かであった。その時、青木氏は「自分の全存在がありのままに認められたように思え」、同時に「この仕事をこのまま続けていけそうな気がした」のだった――。
実は、この原稿を書く少し前に、故郷に住む父が急逝した。ごく個人的な身内の話になるが、どうかご海容のほどを。
父の「納棺」は、亡くなった翌日に行われた。予定時刻を少し過ぎて、白衣を身に着けた真面目そうな青年が二人、父の眠る部屋に静かに入ってきた。そして私たち遺族が緊張して見守るなか、張り詰めた空気が少し動き、聖なる儀式が始まった。私には、その仕事は大変な重労働に思えたが、二人の青年は丁寧にかつ真摯に対してくれた。それは、生真面目で人一倍責任感の強かった父の尊厳を守るにふさわしい、実に気持ちの行き届いたものであった。
後で聞くと、中国地方でこの仕事に専門で従事している人は、見習いを入れても六名しかいないとのことだった。この人たちも青木氏と同様に、「死」や「死者」に対する思い、またこの仕事への心の葛藤を経て今があるのだろうか。たまたまの巡り合わせで、この二人の青年が父の「納棺」を担当してくれたのだが、母も姉も妹も、私達は癒され、感謝の気持ちでいっぱいになったのである。改めて、そのことを若いお二人に伝えたい。 ――河瀬 隆
情報誌CEL